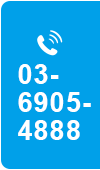近年、スマートフォンやタブレット、携帯ゲーム機の普及により、大人から子どもまで「ゲームを長時間楽しむ」ことが当たり前になってきました。
その一方で、「子どもがゲームをやりすぎて視力が下がった気がする」「大人になってからも目が疲れて視力が落ちてきた」などの相談が増えています。
果たして、ゲームは本当に視力低下の原因になるのでしょうか?また、予防する方法や、すでに視力が下がってしまった場合にできる治療にはどのようなものがあるのでしょうか?
本記事では、ゲームと視力低下の関係性を医学的な視点から解説していきます。
さらに「あおぞらクリニック眼科形成外科」で行っている近視進行抑制の治療(低濃度アトロピン点眼やオルソケラトロジー)についてもご紹介します。

目次
ゲームは本当に視力低下の原因になる?
「ゲームそのもの」が直接の原因ではありません。ただし、長時間の近距離作業が続くと、眼精疲労・仮性近視・近視進行が起こりやすくなります。成長期のお子さまは眼球が発育途中のため、過度な近距離作業が眼軸長(眼球が縦に伸びること)を促し、近視が進むリスクが高まります。
大人は眼球の成長が止まっており急速な近視進行は少ない一方、ドライアイ・眼精疲労・頭痛・肩こりなどの不調が出やすくなります。
ゲームによる視力低下のメカニズム
・ピント調節の疲労:近くを見続けると毛様体筋が緊張し、遠方が一時的にぼやける仮性近視が起こる。
・姿勢・距離:画面を近づける習慣は負担増に直結、進行リスクが上がる。
・睡眠不足:眼の回復が妨げられ、日中の見え方や集中力にも影響。
ゲーム時間は「だらだら長く」ではなく、区切って短くがコツです。タイマーや家庭内ルールを活用しましょう。
子どもと大人で異なる影響
子どもの場合
眼球が伸びやすい時期。学校検診で急にC・D判定が出ることも。屋外活動が少ないお子さんほどリスクは上がります。
また、近見刺激に関係なく、近視進行はある程度骨格に依存するため、ご両親が強度近視であればお子さんも遺伝性をもって近視が進行することも考えられています。
大人の場合
近視の進行は緩やかでも、作業負荷からくる眼精疲労・ドライアイが生活の質に影響。ケアの継続が重要です。
また、高齢者に関しては白内障により近視度数が強くなる傾向があります。
この近視進行に関しては水晶体の混濁によるもののため、眼軸長の変動は起きません。
ゲームによる視力低下を防ぐ方法
・20-20-20ルール:20分ごとに5m先を20秒見る。
・距離は30cm以上:子どもは顔を近づけがち。家族の声かけで習慣化。
・明るい環境で:暗所では瞳孔が開き負担増。室内照明を適切に。
・屋外活動:自然光下の活動時間が長い子ほど、遠視性デフォーカスを防ぎ近視進行のファクターを回避できます。
目安:小学生は1日1時間程度/中高生は学業・睡眠とのバランス優先。週末にまとめて長時間は避け、こまめに休憩を取りましょう。
保護者ができるサポート
お子さまが自分で時間を管理するのは難しいため、保護者のサポートが欠かせません。
例えば「ゲームは宿題や屋外活動が終わってから」「夜9時以降は控える」といったルールを徹底することが有効です。
休日は外遊びやスポーツを意識的に取り入れると、視力維持だけでなく心身の健康にもプラスになります。
眼鏡で近視が進む?遠視性デフォーカスの疑問
「眼鏡をかけると近視が進むのでは?」という疑問は、遠視性デフォーカス(像が網膜の後方に結びやすい状態)に関係します。
近年の研究では、遠視性デフォーカスが眼軸長を促し近視進行に影響する可能性が指摘されています。
これを踏まえて、特殊設計の眼鏡やコンタクトレンズが開発・研究されていますが、現時点では標準治療として確立していません。
一方で、極端に裸眼で見えにくい状態のまま放置してしまうのも画面を近づける原因となり、かえってリスクを高める側面もあります。
つまり、お子さんの目の状態によってては眼鏡をしていたがいいケースと裸眼のほうが良いケース、どちらもあり得るということです。
そのため実生活では、適正度数の眼鏡やコンタクトで正しい距離を保ちつつ、低濃度アトロピン点眼やオルソケラトロジーなどエビデンスのある近視抑制治療を併用することが推奨されます。
当院でも最新の知見を踏まえつつ、安全で確実性の高い治療を提供しています。

視力低下が気になったら受けるべき検査
・視力検査/屈折検査(近視・遠視・乱視の程度)
・眼底検査・OCT(黄斑や視神経の評価)
・角膜形状解析(オルソケラトロジーの適応確認)
当院の近視進行抑制治療
低濃度アトロピン点眼
就寝前に用いる低濃度アトロピン(0.01~0.025%)は、近視進行の抑制が世界的に報告されています。副作用が比較的少なく、小児から使用可能です。
生活習慣の改善と併用することで、より効果的に進行を抑えられます。
オルソケラトロジー(ナイトコンタクトレンズ)
就寝中に特殊設計のレンズで角膜形状を一時的に整え、日中は裸眼で生活できます。
視力矯正と同時に、近視進行抑制効果も期待できます。角膜の形状や涙液の状態を確認し、定期フォローを行うことが前提となります。
Q&A よくある質問
さらに知りたい:家でできる目の休め方
- ゲームや学習は「45〜60分→休憩5〜10分」を基本に。
- 休憩時は窓の外や空の遠景を見る(5m以上が理想)。
- 夜は画面の明るさを控えめにし、就寝1時間前はスクリーンオフ。
まとめ
・ゲーム自体が直接原因ではなく、ポイントは近距離作業の長さと環境。
・20-20-20ルールや適性距離、屋外活動で予防が可能。
・保護者のサポートで生活習慣を整えることが重要。
・遠視性デフォーカスを考慮しつつ、適正矯正+近視抑制治療を選択。
・当院では低濃度アトロピン点眼・オルソケラトロジーを中心に、個別に合った治療プランを提供しています。
お困りごと・ご相談の際はお気軽にご来院ください。
ご予約はこちら(あおぞらクリニック眼科形成外科)